ぬいぐるみ、どんどん増えていませんか?可愛くて手放すのが難しいですよね。
ぬいぐるみが増えると部屋が狭くなってしまうけど、思い出がいっぱいで捨てられないことも多いもの。
今回は、「ぬいぐるみを手放す5つの方法」と、「子どもと一緒にスムーズに整理するコツ」をご紹介します!
ぬいぐるみを手放すタイミングとは?
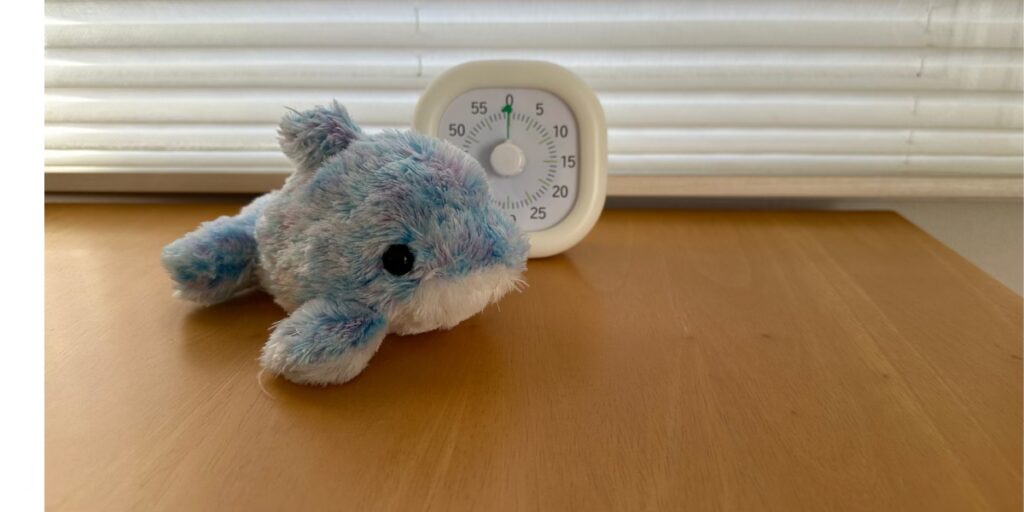
新しいぬいぐるみが増えたときや、子どもが他のものに興味を持ち始めたときが、手放す良いタイミングになります。そんなときは、以下の5つの方法で整理してみてください!
1. 新しいぬいぐるみが増えたとき
新しいぬいぐるみが仲間入りしたタイミングで、「この子のお部屋のスペースを作らなきゃ!」という流れで整理を進めるのがおすすめ。
「新しいお友達のために、古い子はありがとうってバイバイしようか?」と子どもに聞きながら一緒にルールを決めると、スムーズに進みますよ。
2. ぬいぐるみを使わなくなったとき
子供が成長して、ぬいぐるみにあまり興味を示さなくなった時も整理のいいタイミングです。他のおもちゃや学校で話題になっているモノに興味が移ることも多いので、「もう使わないなら手放そうか」と自然に提案してみると、案外あっさりと手放してくれることもあります。
3. ぬいぐるみが傷んでいるとき
ぬいぐるみで遊びすぎて傷んだり、汚れてしまった時も、手放す良いタイミング。
子供と一緒に「たくさん遊んでくれてありがとう」の気持ちを込めてぬいぐるみとお別れすると、物を大切にする気持ちも育ちます。
4. 子供が「もういらない」と言ったとき
「もういらない」と子どもが言ったときは、手放す絶好のタイミングです。
感謝の気持ちを伝えてお別れすると、物を大切にする心も育ちます。
5. 収納スペースが必要なとき
部屋中にぬいぐるみが溢れてしまったら、いよいよ手放すタイミングです。
新しいぬいぐるみが欲しいとなった時は、『新しい子のお部屋のスペースがないから、どうしようか?』と子どもと一緒に話し合って、どれを手放すか決めるのがおすすめ!
自分で選んで手放すことで、スムーズにぬいぐるみ整理ができます。
ぬいぐるみの手放し方5選
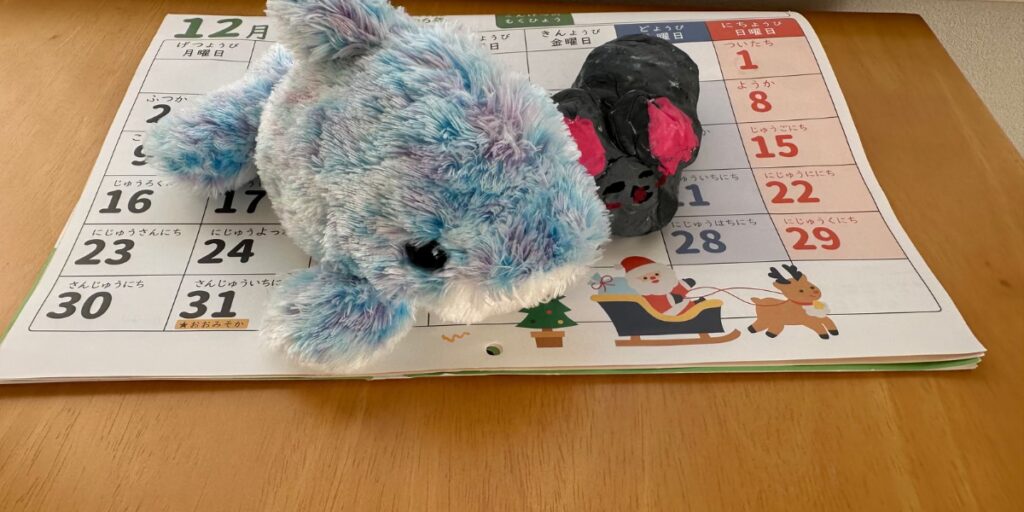
では、具体的にどんな方法でぬいぐるみを手放せるのか、5つの方法をご紹介します。子どもと一緒にできる方法もあるので、ぜひ参考にしてみてください!
1. フリマアプリに出品
状態が良いぬいぐるみなら、フリマアプリに出品するのもおすすめ!
誰かに大事にしてもらって、売上金がちょっとしたお小遣いになるのも嬉しいポイントです!
メリット
- 手軽に出品できる
- 売れれば現金化できる
デメリット
- 出品しても売れないことがある
- 送料や手数料などの手間がかかる
ポイント
ぬいぐるみの状態をよく確認し、写真をきれいに撮ることで売れやすくなります。 商品説明も丁寧に記載し、傷や汚れがあるその場合は正直に・丁寧に伝えることも忘れずに!
2. リサイクルショップに持っていく
忙しいママには、リサイクルショップに持ち込む方法が便利です。
近くにリサイクルショップがあれば、持ち込んでその場で査定を受けられるため、手早く手放すことができます。
メリット
- 店舗に持ち込むだけで簡単に手放せる
- すぐに現金化できる
デメリット
- 買取価格が低いことが多い
- お店によっては買取を行っていない場合もある
ポイント
リサイクルショップに持ち込む前に、ぬいぐるみを洗ってきれいな状態にしておくと、査定額が高くなる可能性があります。清潔感があると、査定が有利になる場合もあるので、ひと手間かけるのがポイント。
3. お焚き上げに出す
ぬいぐるみが古くなっていたり、感謝の気持ちを込めて手放したい場合は、お焚き上げが良い方法です。
近くのお寺や神社で焚き上げが行われているかどうか、事前に確認してみてください。
メリット
- 物に感謝の気持ちを込めて手放せる
- 物を大切にする心を育てられる
デメリット
- お焚き上げができる場所を探すのに手間がかかる
- お焚き上げの費用がかかる場合がある
ポイント
お焚き上げをする前に、子どもにぬいぐるみを大切に使ったことに対して感謝の気持ちを伝えるとより意味のある手放しとなります!
4. 支援団体に寄付する
ぬいぐるみがまだ使える状態であれば、病院や福祉施設、児童養護施設などに寄付することもできます。
必要としている子どもたちに届けることで、手放すことが誰かの役に立つことになります。
メリット
- 子どもたちに喜んでもらえる
- ぬいぐるみを必要とする人に届けられる
デメリット
- 受け入れ先を探す手間がかかる
- 状態によっては受け取ってもらえない場合もある
ポイント
寄付先によって、特定の基準を設けている場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
5. 地域の廃棄ルールに従って処分する
最後は、地域の廃棄ルールに従って処分する方法です。
状態が悪い、あるいは他の方法で処分が難しい場合には、適切な方法で廃棄しましょう。
住んでいる自治体のルールに従い、燃えるゴミや粗大ゴミとして適切に処分することが大切です。
メリット
- すぐに手放せるので、家のスペースを確保できる
- 自分のペースで手放せる
デメリット
- 感情的に手放すのが難しいことがある
- 迷信などが気になる
ポイント
廃棄する前に、「今までありがとう」とぬいぐるみに感謝の気持ちを込めてお別れすることで、気持ちの整理がつきやすくなります。
ぬいぐるみを手放す際のコツ

私がぬいぐるみを整理するとき、一方的に「これは捨てよう」と決めつけることをしないように気をつけています。
子どもの意見や気持ちを尊重しながら「子どもと一緒に」整理を進めていくことが大切です。
そこで手放す際のコツをいくつか紹介します。
1. 子どもに選ばせる
「捨てよう」と言うと、子どもは抵抗を感じることが多いです。
なので、「どれを残したい?」と子どもに選ばせることがポイント。自分で選ぶことで納得し、整理に前向きになります「大切なものを選ぼうね」と、子どもの意見を尊重して進めましょう。
2. ゆっくり進める
いきなりたくさんのぬいぐるみを整理するのではなく、少しずつ進めるのがコツです。 まずは、お気に入りではないぬいぐるみを選んで、残りは少し考えさせる方法が効果的。 子どもも無理なく整理できますよ。
3. 手放した後のことを伝える
ぬいぐるみを整理した後には、「新しいおもちゃのスペースができる」「お部屋がすっきりして遊びやすくなる」など、整理後のメリットを伝えるのがおすすめ。
そうすることで、子どもは整理が終わった後に良い結果をイメージしやすくなり、モチベーションがアップします。
4. 写真に残す
どうしても手放しが難しい場合は、ぬいぐるみと一緒に写真を撮って、思い出として残すのも一つの方法です。写真を見ることで、子どもも「大切にしていたな」という気持ちを思い返すことができ、手放しやすくなります。
また、写真を見せることで、手放した後でも「まだ思い出として持っている」と感じることができるため、気持ちの負担が軽減されます。
5. 手放した後の気持ちをフォローする
ぬいぐるみを手放した後、子どもが悲しむ場合もあります。 その際は、無理に気持ちを押し殺させるのではなく、気持ちに寄り添い、話を聞いてあげることが重要です。
「いつでも思い出として話せるよ」とフォローすることで、子どもの気持ちが落ち着くようになりますよ。
我が家で実践中! ぬいぐるみ整理の「バスケットルール」

ここで、私の家で実際に取り入れているぬいぐるみ整理の方法を紹介します。
「ランドリーバスケット」でぬいぐるみを管理する方法です。
ポイントは、「入ったらなくなったら手放す」というシンプルなルールです。
新しいぬいぐるみが1個増えてバスケットから溢れたら、子供と一緒に「どれを残してどれを手放すか」を考えてもらい、1個手放してもらうようにしています。
子供も自分で選ぶことで、ものの大切さを学びつつ、すっきりと整理できるようになってきています。
ちなみにこのランドリーバスケット。
「メッシュ」になっていて、「蓋つき」なので、ぬいぐるみに埃がつきにくいです!
それに、「取っ手」もついているので、運ぶのに便利ですよ。

まとめ
ぬいぐるみは、子どもの成長とともに変化していくものですが、いつかは手放すタイミングがやってきます。
今回ご紹介した手放し方や整理術を活用して、無理なくお部屋をスッキリと片付けられたら嬉しいです。
ポイントは、「子どもの気持ちを尊重しながら、整理を進めていく」こと!
ぜひ、ぬいぐるみを手放す際には、この方法を試してみてくださいね。

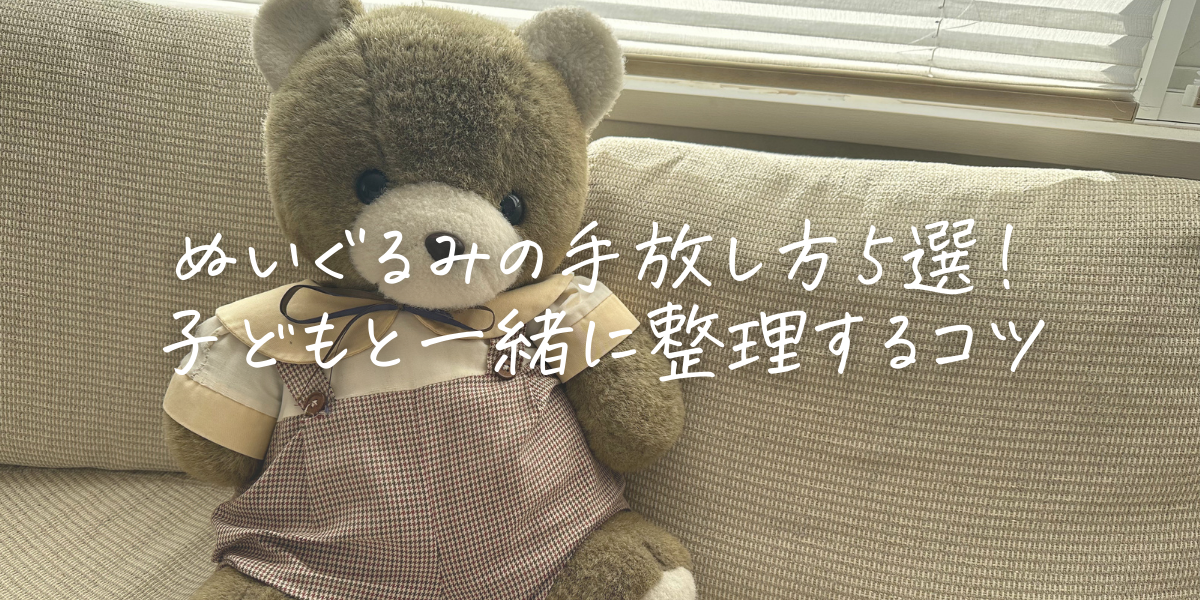
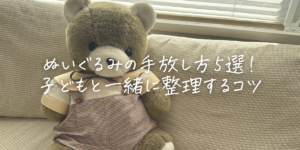
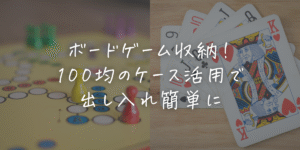

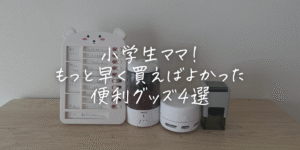
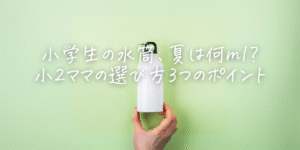
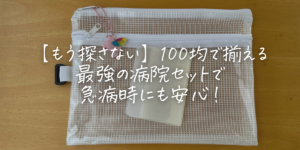
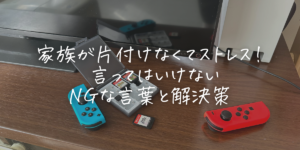
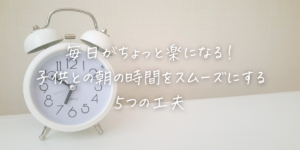
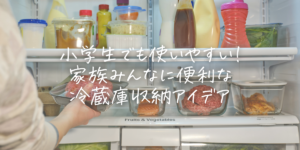
コメント